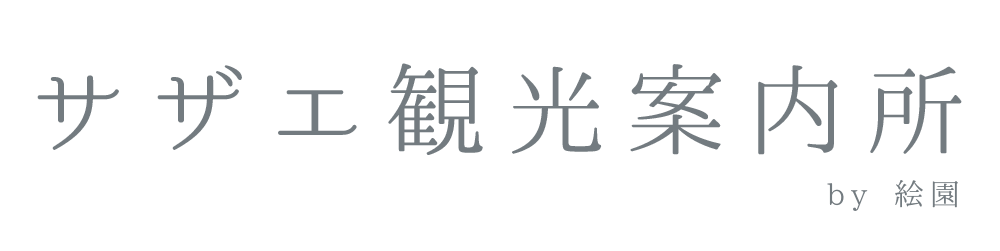訪問地一覧(秋田県)
2014年4月~2014年9月のオープニングでは、秋田県が紹介されました。
地図左上のボタンを押して訪問地名を選択すると、詳細情報や写真等が表示されます。(一部を除く)
【春編】2014年4月~2014年6月
・秋田新幹線こまち
・鳥海山と由利高原鉄道
・角館武家屋敷(仙北市)
・康楽館(小坂町)
・秋田蕗
・じゅんさい摘み(三種町)
・男鹿半島・入道崎(男鹿市)
・田沢湖(仙北市)
・手這坂(八峰町)
・きりたんぽ鍋
・大館曲げわっぱ(大館市)
・本荘ごてんまり(由利本荘市)
・乳頭温泉郷(仙北市)
【秋編】2014年7月~2014年9月
・秋田竿燈まつり(秋田市)
・秋田県立美術館(秋田市)
・象潟九十九島(にかほ市)
・男鹿水族館GAO(男鹿市)
・増田の内蔵(横手市)
・綴子大太鼓祭(北秋田市)
・秋田内陸縦貫鉄道
・あがりこ大王(にかほ市)
・ババヘラアイス
・男鹿のナマハゲ(男鹿市)
・かまくら館(横手市)
・稲庭うどん
・八幡平・大沼(鹿角市)