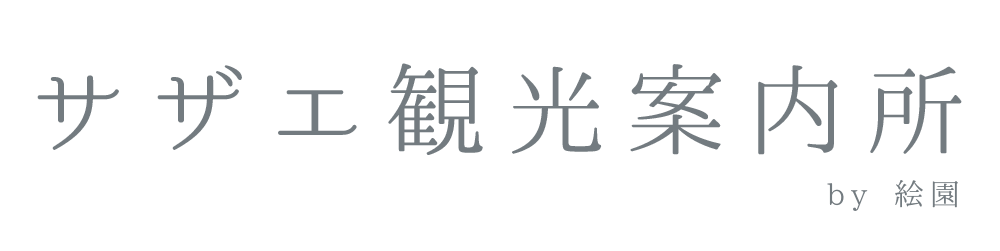訪問地一覧(長野県)
2021年4月~2021年9月のオープニングでは、長野県が紹介されました。
地図左上のボタンを押して訪問地名を選択すると、詳細情報や写真等が表示されます。(一部を除く)
【春編】2021年4月~2021年6月
・飯山菜の花公園(飯山市)
・高遠城址公園(伊那市)
・信州ビーナスライン
・上田電鉄別所線 千曲川に架かる赤い鉄橋(上田市)
・戸隠神社 奥社杉並木(長野市)
・野尻湖 ナウマンゾウの親子像(信濃町)
・北八ヶ岳 苔の森(佐久穂町)
・国宝 松本城(松本市)
・志賀高原 田ノ原湿原(山ノ内町)
・天龍峡大橋 そらさんぽ天龍峡(飯田市)
・布引観音 釈尊寺(小諸市)
・白馬マウンテンハーバーと北アルプス(白馬村)
【秋編】2021年7月~2021年9月
・妻籠宿(南木曽町)
・中央アルプス千畳敷カール
・軽井沢ショー記念礼拝堂(軽井沢町)
・しなの鉄道「ろくもん」
・御代田龍神まつり(御代田町)
・善光寺(長野市)
・上高地 河童橋(松本市)
・大法寺三重塔(青木村)
・ぶどう園
・雷滝(高山村)
・天空の楽園ナイトツアー(阿智村)